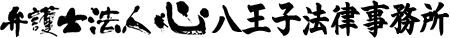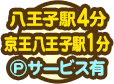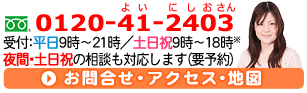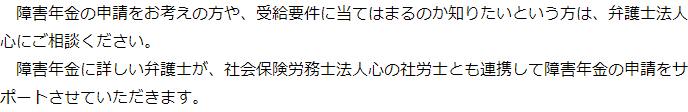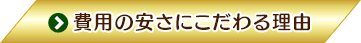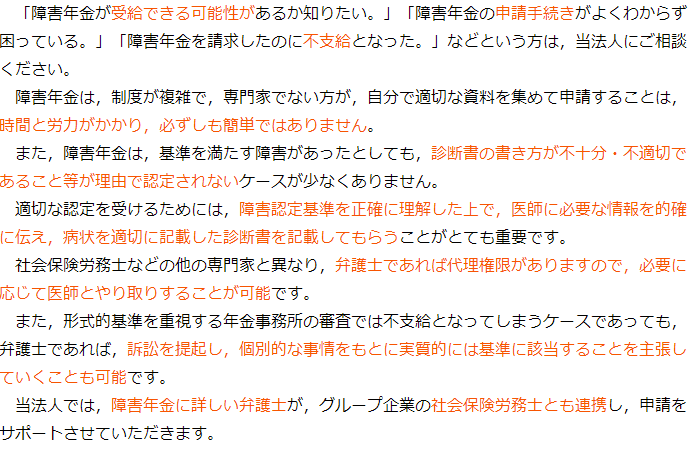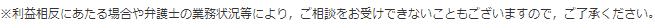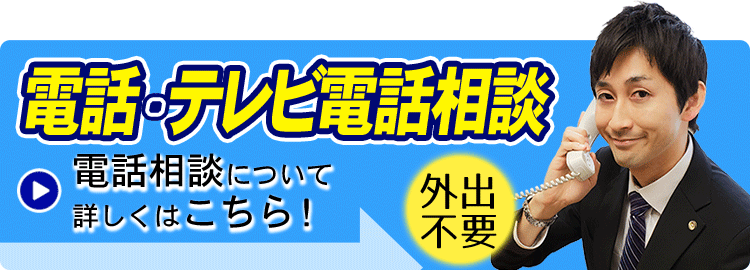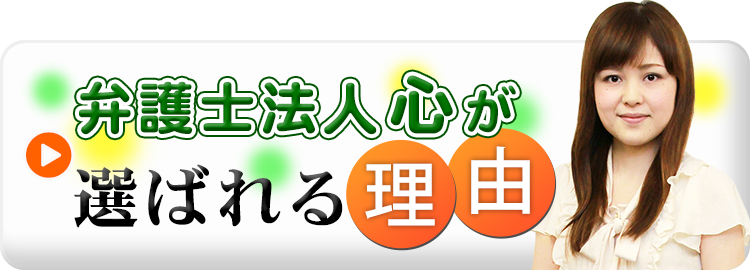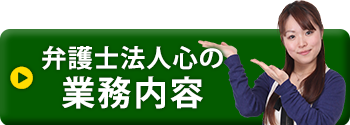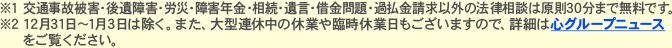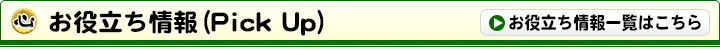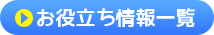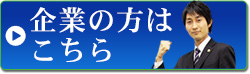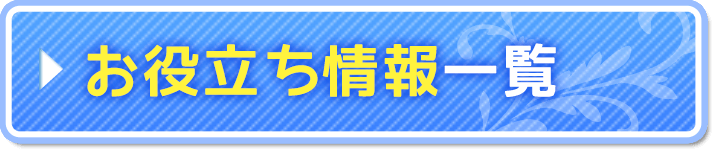障害年金
障害年金を申請する上での注意点
1 障害年金の申請

障害年金を申請する際には、提出が求められている書類を揃えて申請し、要件を満たしていなければ、認定を受けることができません。
書類に間違いや不足があるなどの不備があれば、返戻されて再提出や補正を求められます。
また、書類をそろえて申請をしても、要件を満たしていなければ不支給となりますし、初診日が特定できないなどの場合は、申請が却下されることもあります。
では、障害年金が認定される要件とは、どのようなものなのでしょうか。
2 初診日の要件
障害年金は、申請する傷病に関連する症状で初めて通院した初診日を証明しないと、認定されません。
例えば、健康診断で異常と指摘されたり結果を聞いたりした日は、原則として、初診日にはならず、病院の医師の診療を受けた日が初診日となります。
症状の原因が分からずに、病名が変わりながらいろいろな病院を転々とした後に病名が分かった場合には、原則として、病名が分かっていなくてもその症状で初めて病院に行かれた日が初診日になります。
きちんと病名が判明した日や病名が確定した日ではなく、その症状で初めて病院にかかった日ですので、注意が必要です。
初診日に受診した病院が現在もあってカルテ等がきちんと保管されていれば、病院に受診状況等証明書を作成してもらうことで初診日を証明できます。
しかし、初診の病院が廃院になっていたり、カルテが既に破棄されていたりする場合には、別の方法で初診日を証明しなければならないので、注意が必要です。
3 保険料の納付要件
障害年金が認定されるためには、初診日を基準として、一定の加入期間に一定の保険料を納めていることが必要です。
初診日が判明したら、初診日の前日の時点での年金の納付状況を確認しましょう。
①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、②初診日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないことのどちらかを満たす必要があります。
ただし、公的年金への加入義務のない20歳前に初診日がある場合は、保険料を納める義務はない状態ですので、保険料の納付要件はありません。
4 障害の程度に該当
障害年金は、その傷病による障害の程度が、国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表に明記されている「障害等級」に該当していると認定されなければ、支給されません。
障害の程度は、障害年金申請の際に提出する医師作成の診断書や請求者作成の病歴・就労状況等申立書等の書類をもとにして、日本年金機構の認定医が判断しています。
実際に障害年金を請求してみないと認定されるかどうかが分からないケースも多いですが、弁護士や社会保険労務士が事前に傷病の症状を伺ったり、医師が作成した診断書の内容を確認することで、どの障害のどの等級に当てはまるか、ある程度見当をつけることができることもあります。
5 障害年金のご相談
障害年金の制度は複雑で、初診日をどのように証明するかの判断や決まった書類の代わりに別に書類を出す必要があるかなど、検討するべきことがたくさんあります。
八王子で障害年金の申請を検討されている方は、私たちにご相談ください。
専門家に障害年金を依頼するメリットについて
1 見通しや問題点がわかる

障害年金の制度、受給の要件等は基準があいまいと思われるところがあったり、例外的な取り扱いがあったりして、思った以上に複雑なものといえます。
障害年金の申請をするにあたって、そもそも受給できるのかという見通しや、申請にあたってどういった点が問題となってくるのかということが分かると、それに対してどう対処していけばよいのか等も分かってきます。
例えば、障害年金の受給にあたっては、原則として一定期間以上の保険料の納付の要件を満たしている必要があります。
そのため、未納の期間がどの程度あるかによっては、どんなにしっかり準備をしても、障害年金の受給は認められないことになるため、徒労に終わってしまうことさえあります。
見通しや問題点が把握できるようになることは、専門家に依頼するメリットの1つといえます。
2 適切な等級認定のための準備ができる
適切な等級認定を受けるにあたっては、そのための準備が必要となります。
例えば、精神疾患で障害年金を申請するにあたって、診断書を作成する医師にどのような症状があるかが十分に伝わっていないと、診断書はご自身の実際の症状よりも軽い内容となってしまうことがあります。
適切な等級認定を受けるための準備ができることも、専門家に依頼するメリットの1つということができます。
3 手続きの負担が軽減できる
障害年金の申請にあたっては、診断書以外にも、複数の資料等を準備し、申請書類を整えて提出する必要があります。
そもそも何を集めたらよいか、というところからわからない方の方が多いかと思いますし、それらを調べて準備して、という負担は決して軽いものではありません。
ご自身の症状の推移や入通院、転院の経過や就労状況等をまとめる必要もあります。
これらの作業について、専門家に任せたり、専門家のサポートを受けながら準備を進められたりすることで、申請の負担を減らすことができます。
このように、負担軽減の側面も、専門家に依頼するメリットの1つといえます。
障害年金の種類と金額
1 障害年金の種類

障害年金には、大きく分けて障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
障害基礎年金の中には、若干要件や受給制限等が異なる20歳前障害基礎年金が含まれます。
また、障害厚生年金の受給要件を満たしていて、障害厚生年金の等級よりも軽い症状が残存している場合には、年金とはなりませんが、一時金である「障害手当金」が受給できる場合があります。
2 障害基礎年金の受給額と加算
⑴ 障害年金の受給額
障害基礎年金の受給額は、毎年度ごとに物価等を考慮して改定率をかけてその年度の受給額が定められています。
基準となる金額は、2級が78万0900円、1級がその1.25倍の97万6125円となります。
⑵ 子がいる場合
障害基礎年金には、年収850万円未満で18歳になって最初の3月31日まで(1級または2級の障害がある場合は20歳になるまで)の子がいる場合、基準となる金額に改定率を乗じた金額が加算されます。
基準となる金額は、2人目までは1人につき22万4700円、3人目以降は1人につき7万4900円です。
3 障害厚生年金の受給額と加算
⑴ 障害厚生年金の受給額
障害厚生年金の場合、障害基礎年金の額と比べ、計算内容はかなり複雑になっています。
まず、1級と2級の場合は、障害厚生年金と合わせて、上記2の障害基礎年金の支給が認められることになります(子の加算分も同様です)。
障害厚生年金の金額は、「報酬比例年金額」が基本になります。
細かい計算方法については日本年金機構のページでご確認いただければと思います。
参考リンク:日本年金機構・は行 報酬比例部分
障害厚生年金1級及び2級の場合には、年収850万円未満で65歳未満の配偶者がいる場合、22万4700円(×改定率)の配偶者加給年金も認められます。
⑵ 障害厚生年金3級について
障害厚生年金は3級もありますが、3級の場合は「報酬比例の年金額」のみで、配偶者加給年金はありません。
ただし、最低保障が認められており、報酬比例の年金額が障害基礎年金2級の額の3/4相当額(58万5675円×改定率)を下回る場合は当該額の最低保障額の受給が認められています。
⑶ 障害手当金
障害手当金については、報酬比例の年金額(最低保障額を下回る場合は最低保障額)2年分の一時金の受給とされています。